
”重曹うがい”は口内炎に効くのか? ~口内炎治療あれこれ~

 濱元誠栄院長
濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。
抗がん剤の副作用で、生活の質を大きく下げるものに”口内炎”があります。
その口内炎に重曹が効くかもしれないというお話しです。
抗がん剤の副作用で、生活の質を大きく下げるものに”口内炎”があります。
その口内炎に重曹が効くかもしれないというお話しです。
まずは、保険適応となっている薬剤や治療法について
保険適応の薬剤・治療法
1.痛みの緩和(鎮痛)
- 局所麻酔薬(うがい薬・塗り薬)
- 概要:痛む部分の粘膜を直接麻痺させ、食事や会話の際の痛みを和らげます。食事の前に使用することが多いです。
- 主な薬剤:キシロカイン(リドカイン)を含むうがい薬(含嗽液)やゼリー。
- 粘膜保護剤(物理的バリア)
- 概要: 2018年から保険適用となった比較的新しい治療法です。液体状の薬剤を口に含むと、粘膜の表面でゲル状の保護膜を形成し、口内炎のびらん面を物理的に覆うことで痛みを軽減します。
- 主な薬剤: エピシル®口腔用液(医療機器として保険適用)
- 全身性の鎮痛薬(内服薬)
2.炎症の抑制と粘膜修復
- 抗炎症薬(うがい薬・塗り薬)
- 概要:口腔内の炎症を抑え、粘膜の修復を助けます。
- 主な薬剤:
- アズレンスルホン酸ナトリウム(例: アズノールうがい液など):粘膜の炎症を抑え、修復を促すうがい薬として広く使われます。
- ステロイド: 炎症が強い場合に、患部に直接塗布する薬剤(例: デキサルチン軟膏、デスパコーワ口腔内クリーム、アフタッチ口腔内貼付剤など)が使われることがあります。
3.口腔内の保湿と清浄化
- 保湿剤・人工唾液
- 概要:化学療法により唾液が減少し、口腔内が乾燥すると口内炎が悪化しやすくなります。保湿することで粘膜を保護します。
- 主な薬剤:
- 人工唾液(例: サリベート):唾液の代わりとして口腔内を潤します。ただし、保険適応が頭頸部の放射線照射による唾液腺障害に基づく口腔乾燥症に限定されています。
- 保湿スプレー・ジェル:保険適用の保湿剤が処方されることがあります。
- 含嗽(うがい)
- 概要:口腔内を清潔に保ち、二次感染を防ぐことは非常に重要です。
- 主な薬剤:
- 生理食塩水: 最も刺激が少ないうがい液として推奨されます。
- 上記のアズレンや、感染予防のためのポビドンヨードなどが処方されます(ただし、アルコール含有のものは刺激が強いため避けるべきとされます)。
次に、保険適応外の薬剤や治療法について
- 含嗽(うがい)
- アロプリノール:高尿酸血症で保険適応になっている薬で、抗酸化作用で口内炎にも効果があるという報告があります。
- レバミピド:胃粘膜保護薬で保険適応になっている薬で、口内炎にも効果があるという報告があります。
- カモスタット:経口蛋白分解酵素阻害剤で膵炎の治療に用いられる薬で、口内炎にも効果があるという報告があります。
- 重曹:口腔内のアルカリ化や洗浄の作用をすることで、口内炎による症状を軽減させるという報告があります。
- サプリメント
- L-グルタミン:口腔粘膜のエネルギー源として用いられます。
- その他
- CBD(カンナビジオール):うがいやガム、軟膏などで口腔内の炎症を抑えます。
民間療法は他にもいろいろとありそうですが、ひとまずまとめてみました。
重曹は効果があるというエビデンスと、無いというエビデンスが混在します。うがい程度だとそこまで害は無さそうなので、試してみても良いともいます。
AIに重曹うがいの方法をまとめてもらいました。
1. うがい液の一般的な作り方(濃度)
多くの情報源で示されている一般的な濃度は、約 1% です。
- 作り方の例(約1%濃度):
- 水(または、ぬるま湯) 500 mL(ペットボトル1本分)
- 重曹(炭酸水素ナトリウム) 小さじ 1杯(約 5 g)
- 作り方の例(少量):
- 水(または、ぬるま湯) 100 mL(コップ半分程度)
- 重曹(炭酸水素ナトリウム) 約 1 g
- 注意点:
- 使用する重曹は、食用のもの(ベーキングソーダ)を使用するよう指示されていることが多いです(掃除用のものは不純物が含まれる可能性があるため)。
- 濃度が濃すぎると、かえって粘膜を刺激することがあります。
2. 一般的なうがいの方法
- ぶくぶくうがい(洗口):
- 作ったうがい液を適量(20〜30mL程度)口に含みます。
- 口の中で頬や舌を動かし、液を口腔内全体に行き渡らせるように「ぶくぶく」と約30秒間すすぎます。
- 注意: 口内炎がある場合、喉で行う「ガラガラうがい」は粘膜を傷つける可能性があるため、口の中をすすぐ「ぶくぶくうがい」が推奨されることが多いです。
- 吐き出す:
- うがい液を吐き出します。
- (医療機関の指示によりますが)重曹うがいの後に、水でさらにうがいをする必要はない場合が多いようです。
- 一般的な頻度とタイミング
- 頻度: 1日に4〜6回程度(例:毎食後、寝る前など)
- タイミング: 食後や、口腔内の乾燥・不快感が気になるときなど。
4. その他の一般的な注意点
- 作り置き: 作ったうがい液は、細菌が繁殖する可能性があるため、**その日のうちに使い切る(または1回ごとに作る)**ように推奨されていることが多いです。
- 痛みが強い場合: 重曹うがいでも刺激を感じる(しみる)場合は、無理をせず中止してください。その場合、生理食塩水(水500mLに塩小さじ1杯程度)の方が刺激が少ないとされています。
- 市販のうがい薬: アルコール(エタノール)が含まれる市販のうがい薬は、刺激が強く口内炎を悪化させることがあるため、使用を避けるよう指示されることが多いです。

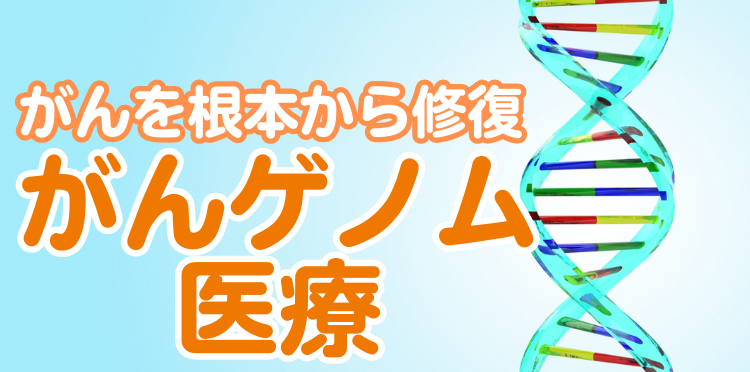

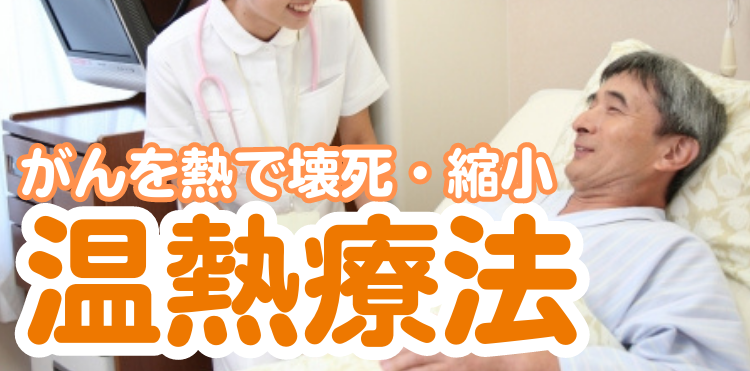






の症例-ー世界膵臓がんデーによせて-300x169.jpg)
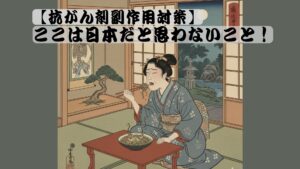

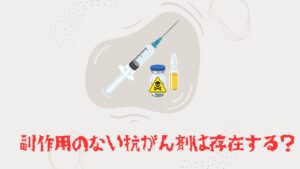

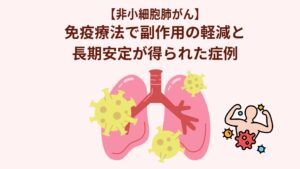
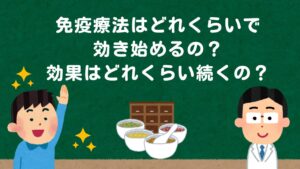
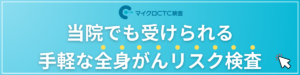
コメント