
「4つの薬で強力治療」のはずが… 新しい治療法がうまくいかなかった理由
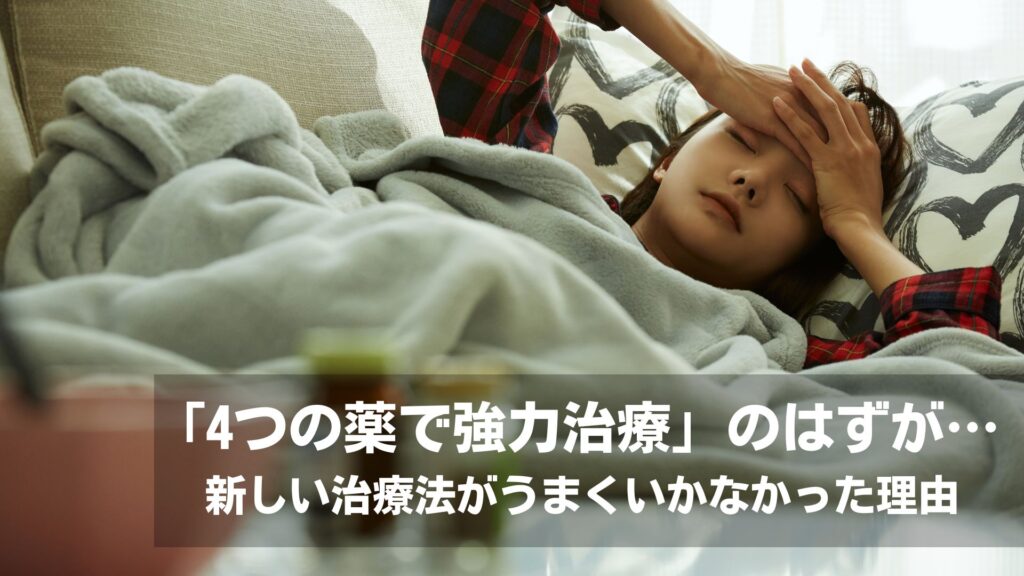
 濱元誠栄院長
濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。
「最新の治療」がうまくいかない時もある
患者さんから「一番強い治療をしてほしい」「新しい薬を全部使ってほしい」と言われることがあります。お気持ちは痛いほどわかります。
ただ、最近とても有名な医学雑誌で、「新しいがん治療の研究」に関する少し残念な結果が報告されました。
それは、「4種類の薬を組み合わせて癌を強力に叩こう」という治療法の研究(臨床試験)でした。 しかし、期待されていたにもかかわらず、その研究は途中で「中止」となってしまいました。


期待した「効果」よりも、「体への負担(副作用)」のほうが重く出てしまったのと先に行われた同様のレジメンが効果を示さなかったいうのが中止になった理由です。
今日はこのお話をきっかけに、治療における「薬の数」と「体への負担」という、とても大切なバランスについてお話ししたいと思います。
なぜ、薬剤を組み合わせるのか?
がん治療では、1種類の薬だけでなく、2種類、3種類と組み合わせて治療することがよくあります。 これにはちゃんとした理由があります。
- 理由1:効果を「1+1=3」にするため 違うタイプの薬が力を合わせることで、1種類ずつ使うよりもずっと大きな効果(相乗効果)が期待できます。
- 理由2:がんの「逃げ道」をふさぐため がん細胞はとても賢く、薬に耐性ができるようになります。複数の薬で色々な方向から攻撃することで、がんが逃げるのを防ぐ狙いがあります。
「それなら、薬は多ければ多いほど良いのでは?」と思うかもしれません。 しかし、ここに「多剤併用療法」の難しさがあります。
薬剤を足し算すると、「良い効果」だけでなく、「体への負担(副作用)」も足し算、あるいは掛け算になってしまうことがあるのです。
- 重い副作用が出やすくなる 薬が増えれば、それだけ体全体が対応しなければなりません。入院が必要になったり、時には命に関わるような重い副作用が出る可能性も高くなります。
- 治療を続けられなくなる 副作用があまりに辛いと、患者さんご本人が「もうやめたい」と感じたり、体が持たずに治療を中断・中止せざるを得なくなります。
- 結果として、元気でいられる時間が延びない 冒頭で紹介した研究のように、たとえがんが少し小さくなったとしても、強い副作用で体調を大きく崩してしまっては、元も子もありません。結果として「元気で長生きする」という一番大切な目標が達成できなくなってしまいます。
3剤→4剤になると逆の結果に
冒頭の臨床試験に先立って行われたLEAP-006試験の結果です。


キイトルーダ+化学療法(2種類)に、数々の臨床試験で結果を出しているレンビマを加えて4剤にすると逆に生存期間が下がっています。
次に化学療法(2種類)にオプジーボ+ヤーボイを加えた日本の臨床試験です。


副作用関連死が多くなり、この試験は途中で中止となりました。
これらの試験結果は、「ただ薬の数を増やして攻撃力を高めれば良いわけではない」ということを明確に示しています。
先日行われた日本肺癌学会でも、やはり4剤は副作用が厳しいというお話しがありました。
なぜ、強力な薬を足したのに、良い結果につながらなかったのでしょうか。
ここで、「抗がん剤治療の根本的な難しさ」についてお話しする必要があります。
風邪薬や血圧の薬と違い、多くの「化学療法(抗がん剤)」は、非常にデリケートな特徴を持っています。 それは、
「がんを叩くのに必要な量(有効量)」と、「体が耐えられなくなる量(副作用が出る量)」の幅が、非常に狭い(近い)
ということです。 私たちはこれを専門用語で「治療域が狭い」と呼びます。
現在の多くの標準治療である3剤併用は、そのギリギリの「さじ加減」の上で、なんとか「効果 > 副作用」のバランスが取れている治療法と言えます。
今回の試験で起きたのは、この絶妙なバランスの上に、「レンビマ」というもう一つの重り(薬)を乗せた結果、バランスが崩れてしまったということだと考えられます。
足した薬(レンビマ)が、もともとギリギリだった化学療法の副作用をさらに強めてしまったのです。 その結果、
- 副作用が強すぎて、治療を続けられなくなった
- 副作用で体力が奪われ、生活の質が著しく下がった
これでは、たとえ癌への攻撃力が少し上がったとしても、結果として「元気に長生きする」というゴールにはたどり着けません。「効果」よりも「毒性」が勝ってしまった典型的な例と言えます。
一番大切なのは「あなたに合った治療」
薬の数が多ければ、一番強い治療というわけでもありません。
今回の臨床試験での教訓をもとにお話ししますと、がん治療で一番大切なこと。それは、
- その治療で、本当に元気でいられる時間が延びるのか?
- その治療を、自分の体力が耐えられるか?
- 治療中も、「その人らしい生活」を送ることができるか?
ということです。
「強い治療=良い治療」とは限りません。 大切なのは「あなたに合った治療」です。
3剤併用でもやはり副作用が強く出ることがあります。その場合は1剤や2剤に減らすべきです。
効果を優先するよりも「自分にとってのベスト」を見つけていきましょう。
今受けている治療や、これから受ける治療について不安なこと、わからないことがあれば、遠慮せずに主治医や看護師、薬剤師に相談してください。

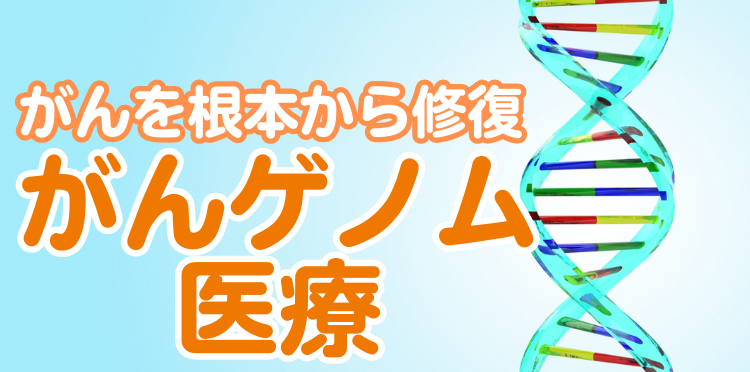

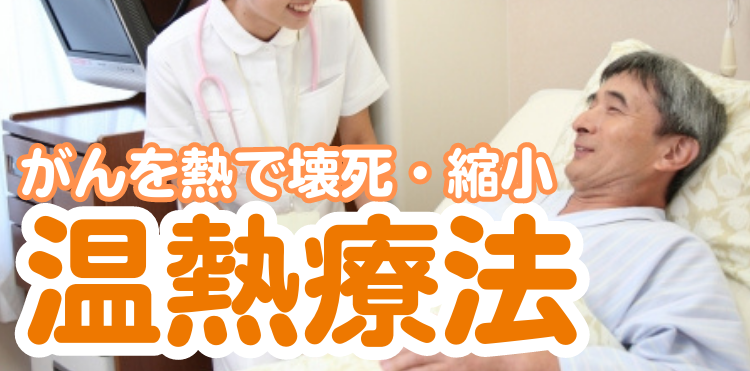






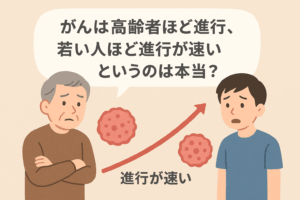
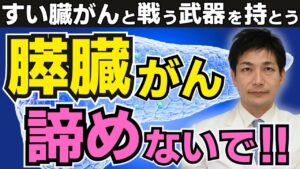
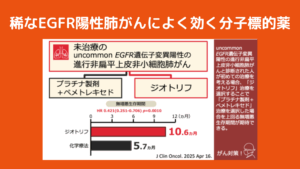


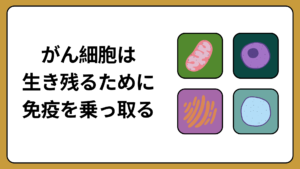
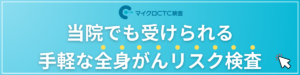
コメント