
【保存版】痔だと思って放置していませんか?肛門がんの初期症状からステージ別治療法、予後まで徹底解説

 濱元誠栄院長
濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。
突然ですが、皆さんにお聞きします。 「お尻の悩み」、抱えていませんか?
排便のときに出血する、お尻に何かが挟まっているような違和感がある、しこりがある……。 こういった症状があるとき、ほとんど方が真っ先に思い浮かべるのは「痔(じ)」だと思います。
「きっと痔だろう」 「恥ずかしいから病院には行きたくない」「痛くも無いので病院はいらない」 「市販薬で様子を見よう」
そう思うのは、とても自然なことです。デリケートな場所ですから、誰だって医師に見せるのは抵抗がありますよね。
しかし、がん治療医としてどうしてもお伝えしたいことがあります。 「痔だと思って手術をしたら、実はがんだった」 というケースが、残念ながら少なからず存在するのです。
肛門がんは、全がんの中の0.1%と希少がんの部類に入る稀ながんで、日本では1年あたり約1000人が罹患すると言われています。また、女性に多く見られます。
今回は、大腸がん(結腸・直腸がん)に比べて情報が少ない「肛門がん」について、どこめよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。 診断の方法から、ステージごとの治療戦略、生存率、そして「人工肛門を避けるための選択肢」まで、かなり踏み込んだ内容になっています。
少し長くなりますが、ご自身やご家族の「もしも」のために、ぜひ最後まで目を通してください。
目次
- 「肛門がん」は「大腸がん」とは別物です
- これがあったら要注意!痔と間違えやすい初期症状
- 原因はウイルス?知っておきたいリスク因子
- 確定診断までの流れ(検査について)
- 肛門がんのステージ(病期)分類
- 切らずに治す?ステージ別の標準治療
- ステージ0〜I期の治療
- ステージII〜III期の治療(ここが最重要)
- ステージIV期の治療
- 気になる予後(生存率)について
- 最後に:恥ずかしがらずに相談を
1. 「肛門がん」は「大腸がん」とは別物です
まず、一番大切な基本からお話しします。 大腸内の便が出る時に最後に通る場所で、「肛門」=「大腸の一部」というイメージを持つ人が少なくありません。しかし、医学的にはこの二つは「性質が異なる別のがん」として扱われます。
組織型(がんのタイプ)が違う
私たちの腸(大腸・直腸)の内側は、粘液を出す「腺細胞」というもので覆われています。ここから発生するがんを「腺がん(せんがん)」と呼びます。一般的な大腸がんは、ほぼこのタイプです。
一方、肛門は皮膚へとつながる出口の部分。ここは「扁平上皮(へんぺいじょうひ)」という、皮膚に近い細胞で覆われています。 そのため、肛門がんの多く(約80〜90%)は「扁平上皮がん」というタイプになります。(海外は腺がんが多い)
- 直腸がん = 腺がん(消化管のがん)
- 肛門がん = 扁平上皮がん(皮膚がんに近い性質)
「タイプが違うと何が変わるの?」と思われるかもしれませんが、これが治療方針を決定づけます。 腺がんは「手術による切除」が第一選択になることが多いのに対し、扁平上皮がんは「放射線や抗がん剤が非常によく効く」という特徴があるのです。
これが、後述する「人工肛門を回避できる可能性」に大きく関わってきます。
2. これがあったら要注意!痔と間違えやすい初期症状
肛門がんは、初期の段階では自覚症状がほとんどないか、あっても軽微です。進行すると以下のような症状が現れますが、これらは良性の病気(痔核、裂肛、痔瘻など)と非常によく似ています。
- 出血: トイレットペーパーに血がつく、便に血が混じる。
- 痛み: 排便時の痛み、あるいは座っている時の持続的な痛み。
- しこり: 肛門の周りに硬いできものが触れる。
- かゆみ・違和感: ムズムズする、残便感がある。
- 便通異常: 便が細くなる、便秘や下痢を繰り返す。
「痔」との見分け方はあるの?
正直に申し上げますと、専門医が診察しても、パッと見ただけでは区別がつかないこともあります。しかし、危険なサインとして以下の点に注意してください。
- 市販薬を使っても治らない 痔であれば、軟膏や座薬を1〜2週間使えば症状が和らぐことがほとんどです。1ヶ月以上続く痛みや出血は、何らかの別の原因を疑うべきです。
- 痛みの質が変わってきた 最初は排便時だけだった痛みが、常にズキズキ痛むようになった場合、がんが周囲の神経や筋肉に浸潤(しんじゅん)している可能性があります。
- 足の付け根(鼠径部)にしこりがある これは肛門がん特有の重要サインです。肛門のリンパ流は、お腹の中だけでなく、足の付け根(鼠径リンパ節)にも流れています。お尻の症状とともに、太ももの付け根にグリグリとしたしこりができた場合は、転移の可能性があります。
3. 原因はウイルス?知っておきたいリスク因子
なぜ、肛門がんになるのでしょうか? 一般的な大腸がんのリスク因子としては、赤身肉の過剰摂取、アルコール、肥満などが挙げられますが、肛門がん(扁平上皮がん)には特殊なリスク因子があります。
それは「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の感染です。
HPV(ヒトパピローマウイルス)と聞くと、「子宮頸がんの原因ウイルス」としてご存知の方も多いでしょう。実は、肛門がんの発生にもこのHPVが深く関与していることが分かっています。 特に、オーラルセックスやアナルセックスなどの性行動によって感染リスクが高まりますが、性交渉の経験がある方なら誰でも感染しうるありふれたウイルスです。
その他のリスク因子としては以下があります。
- 喫煙: 喫煙者は非喫煙者に比べてリスクが数倍高まると言われています。
- 慢性的な炎症: 痔瘻(じろう)を長期間放置して「がん化」するケース(これは腺がんが多いです)。
- 免疫抑制状態: HIV感染者の方や、臓器移植後に免疫抑制剤を使用している方。
4. 確定診断までの流れ(検査について)
「もしかして…」と不安になったら、まずは消化器外科、または肛門科(肛門外科)を受診してください。 当院での一般的な診断の流れをご紹介します。
① 視診・触診(直腸指診)
医師が肛門を目で見て確認し、指を入れて内部の状態を調べます。 「痛くないですか?」と心配されますが、潤滑ゼリーを使用しますので、強い痛みを感じることは少ないです(すでに強い炎症がある場合は配慮します)。指の感覚で、腫瘍の硬さや大きさ、周囲への広がりを確認します。
こちらのサイトに、肛門がんの写真が掲載されていますが、かなり強烈なので苦手な方はクリニックせずに先に進んでください。
② 肛門鏡検査
肛門鏡という短い筒状の器具を使って、内部を直接観察します。
③ 生検(病理組織検査)
がんが疑われる組織の一部をつまみ取り、顕微鏡で詳しく調べます。 これで「がん細胞があるか」「どんな種類のがんか(扁平上皮がんか腺がんか)」が確定します。
④ 画像診断(CT・MRI・PET)
がんであると確定した場合、どのくらい進行しているか(ステージ)を調べるために画像検査を行います。
- CT・MRI: 腫瘍の広がりや、リンパ節転移の有無を調べます。
- PET検査: 全身のどこかに転移が飛んでいないかを確認します。
5. 肛門がんのステージ(病期)分類
治療法を決める上で最も重要なのが「ステージ(病期)」です。 肛門がんのステージは、「T(がんの大きさ・深さ)」「N(リンパ節転移)」「M(遠隔転移)」の組み合わせで決まります。
少し専門的になりますが、ご自身の状況を理解するために重要ですので詳しく書きます。
- ステージ0(上皮内がん): がんがごく浅い粘膜内にとどまっている状態。
- ステージI: がんの大きさが2cm以下で、リンパ節への転移がない。
- ステージII: がんが2cmを超えているが、リンパ節への転移はない。
- IIA期:2cm〜5cm以下
- IIB期:5cmを超えている
- ステージIII: がんの大きさに関わらず、リンパ節転移がある。または、尿道・膀胱・膣などの隣接臓器に広がっている。
- ステージIV: 肝臓、肺、骨など、離れた臓器への転移がある。
6. 切らずに治す?ステージ別の標準治療
ここからが、皆さんが最も知りたい「治療法」の話です。 冒頭でお話しした通り、肛門がん(扁平上皮がん)の治療は、近年劇的に変化しています。
かつては、肛門をすべて取り除き、永久的な人工肛門(ストーマ)を作る手術(直腸切断術)が唯一の根治治療でした。 しかし現在は、「肛門機能を温存すること」が治療の大きな目標になっています。
■ ステージ0、ごく一部のステージI
がんが非常に小さく、かつ肛門の筋肉(括約筋)に食い込んでいない場合に限り、「局所切除術」が行われます。 これは、肛門そのものは残し、がんの部分だけをくり抜く手術です。体への負担も少なく、排便機能も維持されます。
■ ステージI、II、III(※ここが一番多いケース)
ここが最も重要なポイントです。 ステージI(2cm以下でも筋肉に近い場合)から、リンパ節転移のあるステージIIIまで。 世界のガイドラインで推奨されている標準治療は、「化学放射線療法(CCRT)」です。
これは手術ではありません。「抗がん剤(飲み薬や点滴)」と「放射線治療」を同時に行う治療法です。
【なぜ手術じゃないの?】 扁平上皮がんは放射線や抗がん剤が非常によく効くため、メスを入れなくてもがんを消滅させられる可能性が高いからです。 この治療法の最大のメリットは、「人工肛門にならずに、自分の肛門で排便できる生活を守れる」こと。 欧米の研究や日本の臨床データでも、約70〜80%以上の患者さんが、この治療だけでがんを消失させ、人工肛門を回避できているという結果が出ています。
たとえステージIIIでリンパ節転移があっても、まずは手術ではなく、この化学放射線療法を行うのがセオリーです。
【具体的な治療内容】
- 期間: 約1ヶ月半〜2ヶ月程度。
- 放射線: 平日に毎日、骨盤全体(および鼠径部)に照射します。
- 抗がん剤: 一般的に「5-FU(フルオロウラシル)」と「マイトマイシンC」という2種類の薬を併用します。
【副作用について】 決して楽な治療ではありません。 放射線の影響で肛門周囲の皮膚がただれて痛む(皮膚炎)、排便時の痛み、下痢、頻尿などが起こります。また、抗がん剤による吐き気や白血球減少なども起こり得ます。 しかし、治療が終われば皮膚炎などは徐々に回復します。「肛門を失う」というリスクと天秤にかければ、乗り越える価値のある治療と言えるでしょう。
【もし効果がなかったら?】 化学放射線療法を行ってもがんが消え残った場合や、一度消えても再発した場合には、「救済手術」として直腸切断術(人工肛門造設)が行われます。
■ ステージIV
肝臓や肺などに転移がある場合は、全身に効果を行き渡らせるための「全身化学療法(抗がん剤治療)」が主体となります。
日本には肛門がんのガイドラインも無く、実は肛門がんで承認された抗がん剤というのが存在しません。
アメリカのガイドラインを参考に、ステージ1ー3では5-FU+マイトマイシンCを、ステージ4ではパクリタキセル+カルボプラチンを特例で使用しているのが現状です。
そんな現状を変えるべく、日本も参加した国際共同臨床試験が行われ、免疫チェックポイント阻害薬ジニイズ(レチファンリマブ)+抗がん剤が近々承認される予定です。


ちなみに、出血や痛みがひどくて生活に支障がある場合には、症状を和らげるための緩和的な放射線治療や、便の通り道を変えるための人工肛門造設を行うこともあります。
7. 気になる予後(生存率)について
「がんと診断されたら、あとどのくらい生きられるのか」 数字を見るのは怖いかもしれませんが、正しく恐れるための目安としてお伝えします。
米国のデータ(SEER)などに基づく5年相対生存率の目安は以下の通りです。
- 限局(がんが原発巣にとどまっている):約80%以上
- 領域リンパ節転移あり(ステージIIIなど):約60〜70%
- 遠隔転移あり(ステージIV):約30%前後
この成績は、消化器がんの中では比較的治療の反応が良い部類に入ります。
また、重要なのが「人工肛門を回避できた割合です」
化学放射線療法が効かなかったり、局所再発した場合には人工肛門造設術が行われます。
日本人の調査で、ステージ2-3で化学放射線療法を行った患者さんが、人工肛門なしで5年生存している割合が73.0%と高い結果が出ていました。
8. 最後に:恥ずかしがらずに相談を
長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。
肛門がんは、早期に見つければ、高い確率で「肛門を残したまま治せる」病気です。 しかし、場所が場所だけに、受診をためらって進行させてしまう方が後を絶ちません。
「お尻を見せるのが恥ずかしい」 その気持ちは本当によく分かります。 ですが、私たち医師にとっては、お尻も目や耳と同じ、治療すべき大切な体の一部にすぎません。恥ずかしがる必要は全くないのです。
「恥ずかしさ」よりも「あなたの命」と「これからの生活」の方が、ずっとずっと大切です。
もし、お尻の症状で悩んでいるなら、 「どうせ痔だろう」と自己判断せず、勇気を出して専門医の扉を叩いてください。
そして、もし万が一「肛門がん」と診断され、治療法に迷ったり、主治医の説明に不安を感じたりしたときは、セカンドオピニオンとして当院にご相談ください。 標準治療から最新の免疫療法まで、あなたの希望に沿った治療の道筋を、一緒に考えていきましょう。
ひとりで悩まずに、銀座みやこクリニックへご相談ください。

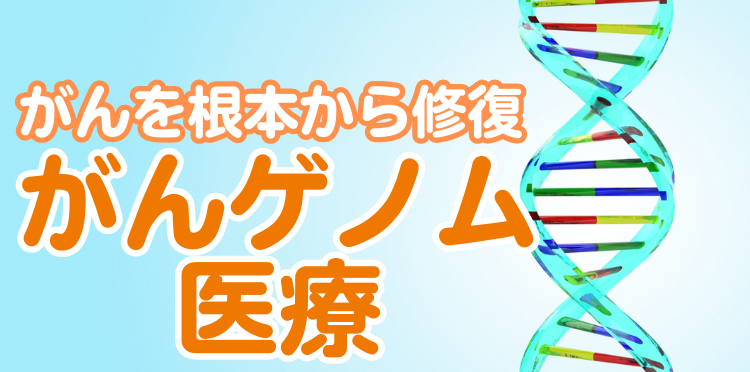

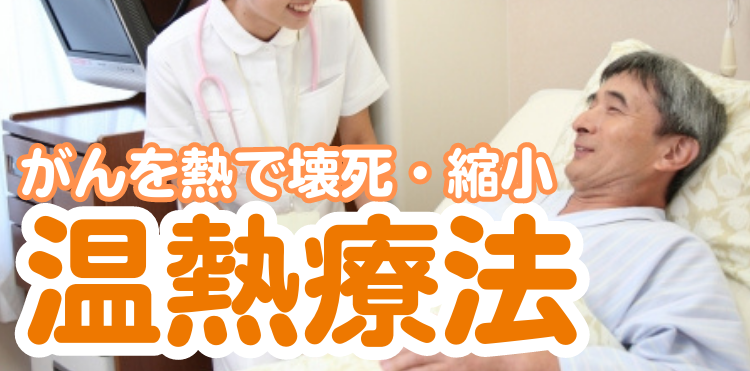





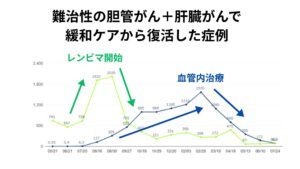

の症例-ー世界膵臓がんデーによせて-300x169.jpg)
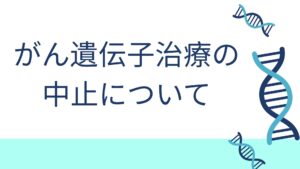
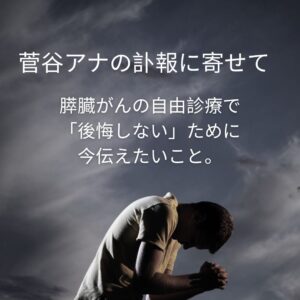



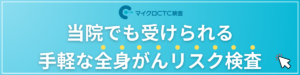
コメント