
副作用のない抗がん剤が開発されている?
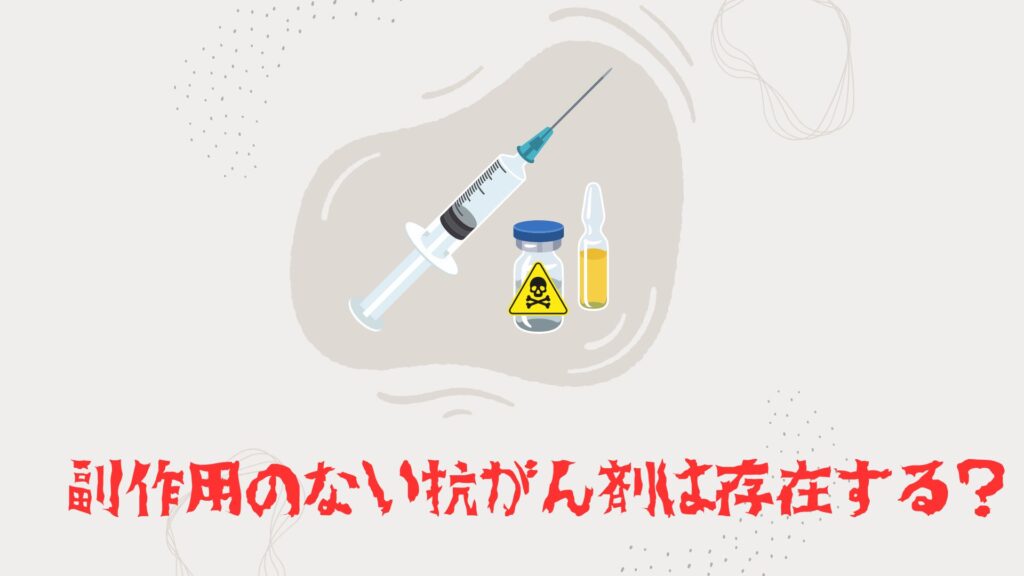
 濱元誠栄院長
濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。
あるセミナーで出したクイズの1題です。
抗がん剤治療というと、皆さんイメージするのがまず「髪の毛が抜ける」「ゲーゲー吐く」だと思います。
実際には、薬剤によって髪が抜けたり抜けなかったり、吐き気があったりなかったと、その抗がん剤に特有の副作用というのがあります。
まずは抗がん剤治療で見られるすべての副作用について、AIにまとめてもらいました。ちなみに、ここでいう抗がん剤とは、殺細胞性の一般的な抗がん剤のことを言います。
抗がん剤の副作用について
1. 消化器系の副作用
消化管の粘膜は細胞分裂が盛んなため、抗がん剤の影響を受けやすい部位です。
- 吐き気・嘔吐 (悪心・嘔吐)
- 症状: ムカムカする不快感、実際に吐いてしまう。
- 原因: 脳の嘔吐中枢が刺激されることや、消化管の粘膜がダメージを受けることによって起こります。
- ポイント: 現在では、吐き気止めの薬(制吐剤)が発達しており、予防的に使用することで症状をかなり抑えることができます。
- 食欲不振
- 症状: 食欲がわかない、何も食べたくない。
- 原因: 吐き気や倦怠感、味覚の変化などが複合的に影響して起こります。
- 下痢・便秘
- 症状:
- 下痢: 便がゆるくなり、回数が増える。ひどい場合は水のような便になることもあります。
- 便秘: 排便が困難になる、便が硬くなる。
- 原因:
- 下痢: 腸の粘膜がダメージを受けて炎症を起こすため。
- 便秘: 腸の動きが鈍くなることや、使用する薬の種類によって起こります。
- 症状:
- 口内炎
- 症状: 口の中や舌に潰瘍やただれができる、痛みで食事がしにくくなる。
- 原因: 口の中の粘膜の細胞が、抗がん剤によってダメージを受けるため。
2. 血液系の副作用(骨髄抑制)
骨髄は、血液をつくる働きをしています。抗がん剤は、この骨髄の働きを抑えてしまうことがあります。
- 白血球減少
- 症状: 発熱、悪寒(さむけ)など。免疫力が低下するため、感染症にかかりやすくなります。
- 原因: 骨髄でつくられる白血球が減少するため。
- 貧血
- 症状: めまい、立ちくらみ、ふらつき、息切れ、だるさなど。
- 原因: 血液中の赤血球が減少するため。
- 血小板減少
- 症状: 鼻血、歯ぐきからの出血、皮膚に青あざ(内出血)ができやすくなるなど。
- 原因: 血液を固める働きをする血小板が減少するため。
3. 全身性の副作用
- 全身倦怠感(けんたいかん)
- 症状: 全身がだるい、疲れやすい、体が重く感じる。
- 原因: 治療による身体的な負担や、精神的なストレス、貧血、臓器機能の低下などが複合的に影響します。
- 脱毛
- 症状: 髪の毛が抜ける。場合によっては、眉毛やまつ毛、体毛も抜けることがあります。
- 原因: 毛根の細胞は活発に分裂するため、抗がん剤の影響を受けやすいです。治療が終われば、徐々に再び生えてきます。
- アレルギー反応
- 症状:一般的なアレルギー反応からアナフィラキシーショックまで様々です。
- 原因:薬剤へのアレルギーで起こります。初回の投与直後に起こることが多いですが、複数回投与後や、投与後数日してから起こることもあります。
4. 皮膚・爪の副作用
- 皮膚障害
- 症状: 発疹、皮膚の乾燥、かゆみ、色素沈着など。
- 原因: 皮膚の細胞や機能が、抗がん剤によって影響を受けるため。
- 手足症候群(手掌足底紅斑)
- 症状: 手のひらや足の裏が赤くなったり、腫れたり、皮がむけたり、ひどい場合は水ぶくれができたりします。痛みやかゆみを伴うこともあります。
- 原因: 特定の抗がん剤が、手足の毛細血管に集まりやすいことで起こると考えられています。
- 爪の変化
- 症状: 爪の色が黒ずむ、ひび割れ、変形など。
- 原因: 爪をつくる細胞に抗がん剤が影響するため。
5. 神経系の副作用
- 末梢神経障害
- 症状: 手や足の指先がピリピリとしびれる、感覚が鈍くなる、物がつかみにくくなる、ボタンがかけにくいなど。
- 原因: 抗がん剤が末梢神経にダメージを与えるため。症状の出方や程度には個人差があり、治療終了後も症状が残る場合もあります。
- 味覚障害
- 症状: 味が薄く感じる、何も味がしない、金属のような変な味がするなど。
- 原因: 舌にある味を感じる細胞がダメージを受けたり、唾液が減少したりすることで起こります。
以上が、抗がん剤でみられる副作用のまとめです。
抗がん剤の副作用は、患者さん一人ひとりの体質や、使用する薬の種類、投与量、治療期間によって大きく異なりますが、がんだけでなく正常細胞も必ず攻撃するため、必ず何らかの副作用が出ます
また、近年、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった抗がん剤とは異なる機序のがん治療薬が登場しており、従来の抗がん剤とは異なる副作用が見られることがあります。
抗がん剤以外のがん治療薬の副作用とは
分子標的薬は、がん細胞特有の分子(ターゲット)を狙い撃ちすることで、従来の抗がん剤よりも正常な細胞への影響を抑えるように設計された治療薬です。ブログ記事に使えるように、その特徴と種類をまとめました。
①分子標的薬とは?
分子標的薬は、がん細胞の増殖や生存に関わる特定の分子(タンパク質や遺伝子など)の働きをピンポイントで妨害する薬です。
従来の抗がん剤との違い
- 分子標的薬: がん細胞にだけ存在する、またはがん細胞で特に活発に働いている分子を標的とするため、正常な細胞への影響が少なく、副作用が比較的マイルドになる傾向があります。
分子標的薬の種類と作用の仕組み
分子標的薬は、標的とする分子の種類や作用の仕方によって、大きく以下の3つに分類できます。
1. チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)
- 作用の仕組み: 細胞内にある「チロシンキナーゼ」という酵素の働きをブロックします。この酵素は、がん細胞の増殖や生存に不可欠な信号を伝達する役割を担っています。この信号伝達を止めることで、がん細胞を死滅させたり、増殖を抑制したりします。
- 特徴: 錠剤やカプセルの形で、内服薬として使われることが多いです。
- 例: 非小細胞肺がん、慢性骨髄性白血病、腎細胞がんなどの治療に使われます。
2. モノクローナル抗体
- 作用の仕組み: がん細胞の表面に存在する特定のタンパク質を標的とし、これに結合するように作られた人工的な抗体です。抗体ががん細胞に結合することで、がん細胞の増殖を促す信号を妨害したり、免疫細胞ががん細胞を攻撃するのを助けたりします。
- 特徴: 注射薬として、点滴で投与されるのが一般的です。
- 例: 乳がん、大腸がん、非ホジキンリンパ腫などの治療に使われます。
3. その他
上記以外にも、がん細胞の成長を助ける新しい血管の形成を妨害する「血管新生阻害薬」や、がん細胞が持つ遺伝子を標的とする薬など、さまざまなタイプの分子標的薬があります。
分子標的薬の副作用
分子標的薬は従来の抗がん剤よりも副作用が少ないとされますが、全くないわけではありません。標的とする分子によっては、正常な細胞にもわずかに存在するため、その働きが妨げられることで副作用が起こります。
- 皮膚の症状: 発疹、ニキビのような吹き出物、皮膚の乾燥、かゆみなど。
- 手足症候群: 手のひらや足の裏の皮膚が赤くなったり、むけたりする。
- 消化器系の症状: 下痢、吐き気、食欲不振など。
- その他: 倦怠感、高血圧、肝機能障害など。
次に、免疫チェックポイント阻害薬の副作用について
②免疫チェックポイント阻害薬とは?副作用の特徴は?
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞によって抑えられていた免疫細胞(T細胞など)のブレーキを外し、再びがんを攻撃させる新しいタイプのがん治療薬です。 しかし、免疫の働きが活発になりすぎることで、がん細胞だけでなく正常な細胞まで攻撃してしまうことがあります。この特有の副作用は「免疫関連有害事象(irAE:Immune-related Adverse Events)」と呼ばれ、全身のさまざまな臓器に炎症を起こす可能性があります。
従来の抗がん剤とは異なり、irAEは投与後しばらくしてから、あるいは治療終了後に現れることもあり、症状に気づくのが遅れると重症化するリスクがあるため、注意が必要です。
免疫関連有害事象(irAE)の主な症状(体の部位・機能別)
免疫関連有害事象は、自己免疫疾患の症状と似ているのが特徴です。ここでは、特に注意すべき主な症状をまとめました。
1. 皮膚の副作用
- 症状: 発疹、かゆみ、皮膚が赤く腫れる、白斑(皮膚の一部が白く抜ける)など。
- 特徴: 比較的早期(治療開始から数週間~数ヶ月)に現れることが多いとされますが、いつ発症してもおかしくありません。
2. 消化器系の副作用
- 症状:
- 大腸炎: 持続する下痢、腹痛、血便、粘液便など。
- 肝機能障害・肝炎: 全身倦怠感、だるさ、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)など。
- 特徴: 腸の炎症によって下痢が起こりやすく、通常の止痢剤(下痢止め)では悪化することもあるため、自己判断で服用しないことが重要です。
3. 呼吸器系の副作用
- 症状:
- 間質性肺炎: 息切れ、乾いた咳(痰を伴わない咳)、発熱、呼吸困難など。
- 特徴: 非常に重篤な副作用の一つです。風邪と似た症状から始まることが多く、見過ごされがちです。少しでも息苦しさを感じたら、すぐに医療機関に連絡することが大切です。
4. 内分泌系の副作用(ホルモンをつくる臓器の障害)
- 症状:
- 甲状腺機能障害:
- 機能低下: 疲れやすい、寒がりになる、便秘、むくみ、体重増加など。
- 機能亢進(中毒症): 動悸、多汗、下痢、体重減少、手の震えなど。
- 下垂体機能障害: 倦怠感、食欲不振、吐き気、低血圧など。
- 1型糖尿病: のどの渇き、多尿、全身倦怠感、体重減少など。
- 甲状腺機能障害:
- 特徴: 血液検査で発見されることが多いため、自覚症状がない場合もあります。症状がゆっくりと進行することが多く、気づきにくいことがあります。
5. 神経・筋肉系の副作用
- 症状:
- 筋炎・心筋炎: 筋肉痛、筋力低下、動悸、息切れ、胸の痛みなど。
- 重症筋無力症: まぶたが下がる、物が二重に見える、飲み込みにくい、手足に力が入らないなど。
- 特徴: 筋炎・心筋炎は、急速に悪化し命にかかわることもあるため、特に注意が必要です。
免疫チェックポイント阻害薬の副作用は、従来の抗がん剤のように、投与後すぐに現れるとは限りません。治療を始めて数ヶ月後、あるいは治療が終了した後に発症することもあります。
免疫チェックポイント阻害薬の副作用は免疫細胞によって起こるものなので、対処法は基本的には免疫を抑えるためにステロイドを投与します。
早期に発見し、迅速な対応を行うことが、症状の重症化を防ぐことができます。
特徴的な体調の変化というのがないため、些細な体調の変化にも注意し、普段と違うと感じたことがあれば、すぐに医師や看護師に伝えることが極めて重要です。
まとめ
現在は、昔ながらのいわゆる”抗がん剤”だけでなく、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった様々な種類のがん治療薬が登場し(ウイルスを使った遺伝子治療薬もあります)、副作用も多様化しています。
がん治療を行う薬剤には、大なり小なり必ず副作用があります。
いたずらに副作用を恐れているだけではいけません。
早期に発見、対応し、重症化を防ぐためには患者側にも副作用に対する意識と知識を持つことが重要です。

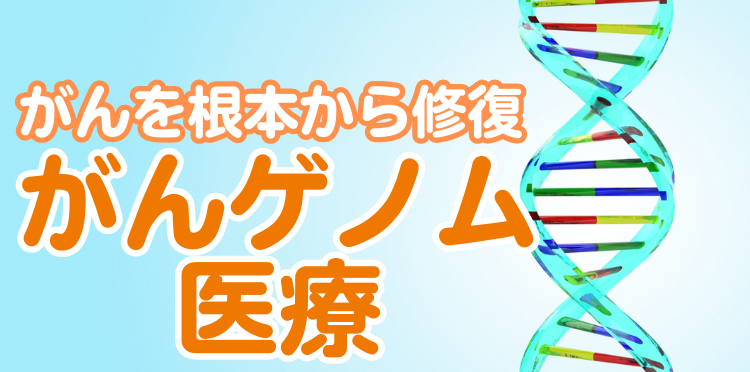

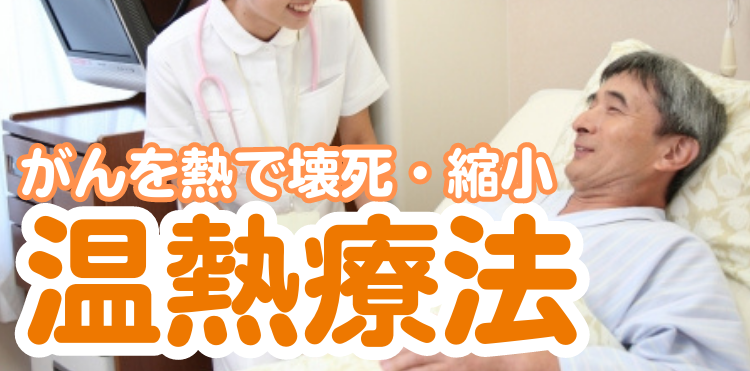









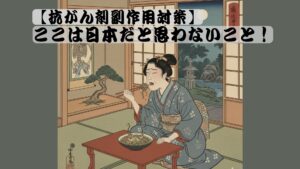



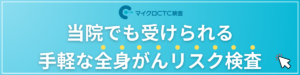
コメント