
がん遺伝子治療の中止について

 濱元誠栄院長
濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。
お気付きの方もいるかもしれませんが、当院をはじめ、がん遺伝子治療を行っていた施設が軒並み治療を中止しました。
その理由は2つの法律にあります。
①再生医療法
②カルタヘナ法
それぞれ解説していきます。
①2025年6月より、遺伝子治療が再生医療法(正式名称 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」)で定める第1種再生医療となりました。
再生医療法では、生命に危険を及ぼすリスクに応じて第1種から第3種まで定められています。
| 分類 | リスクの程度 | 主な内容・具体例 |
| 第1種 | 高リスク | 未知性が高く、生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。(例:iPS細胞、ES細胞、他家(他人)細胞、遺伝子導入細胞) |
| 第2種 | 中リスク | リスクが相当程度あるもの。(例:自家(本人)の幹細胞を培養して使用するもの) |
| 第3種 | 低リスク | リスクが低いと考えられるもの。(例:自家(本人)の体細胞を培養せず使用するもの(PRP療法など)) |
がん領域では、CARーT療法など遺伝子導入を行った細胞治療が第1種に該当し、大学病院やがんセンターレベルでないとできない治療で、クリニックレベルでは不可能です。
これまで当院でも行ってきた遺伝子治療で、CAR-T療法のような重篤な副作用が起こることはまずありませんが、第1種になったため基本的にクリニックではできなくなります。
ちなみに、6種複合免疫療法やがんワクチン療法、NK細胞療法など、自由診療で行われている免疫細胞療法は第3種に該当し、クリニックレベルでも可能です。
②カルタヘナ法は、正式名称を「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」と言い、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることを目的とした法律です。
遺伝子組み換え生物を国内で製造したり輸入したりする時に関わってくる国際的な法律です。
ただ、遺伝子組み換え作物大国であるアメリカやオーストラリアはカルタヘナ法を批准していないし、EUでは医薬品に関しては除外されています。
世界では比較的軽視されている(アメリカなどは無視している)この法律を日本は真面目過ぎるくらいに順守しており、特に日本での遺伝子関連の医薬品開発の妨げになっています。
自由診療で行われているがん遺伝子治療の多くは遺伝子の運び屋としてウイルスベクターを使用しており、それがカルタヘナ法に抵触すると、先日あるクリニックが指摘され問題となりました。
そんなこんなで、日本のクリニックレベルでの遺伝子治療が行えなくなりました。
しかし、抜け道というのもあります。
p53などのDNAに直接作用するものではなく、DNAから合成されたmRNAに作用する核酸医薬というグレー?な遺伝子治療を、①に該当しないという判断で使用するところもあるようです。
また、ウイルスベクターを止めて、プラスミドというカルタヘナ法に抵触しないベクターを用いることで②の対象外になるようにしているところもあるようです。
上記の遺伝子治療をやろうと思えば当院でもできますが
がん抑制遺伝子の王様で最も強力なp53が使えないこと、プラスミドベクターは治療効果が低いことを鑑みると、遺伝子治療を行う意味があまりないと判断しました。
ですから、当院のHPからも削除しましたし、本気で効果を狙った遺伝子治療を行う施設は、軒並み遺伝子治療を中止しています。
効果が低い(と思われる)遺伝子治療にしてまで治療を続けないということが、遺伝子治療の師匠から教わったプライドです。

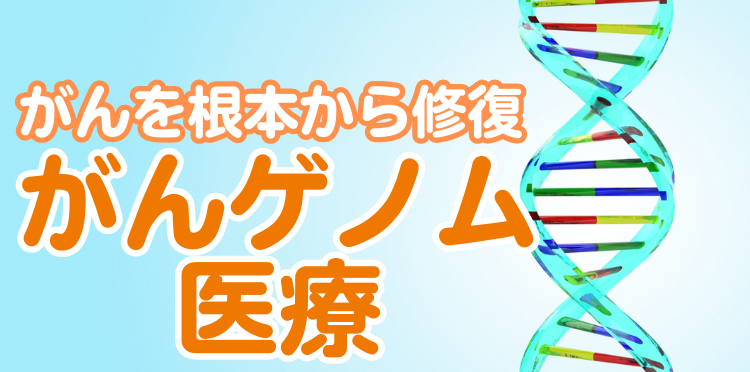

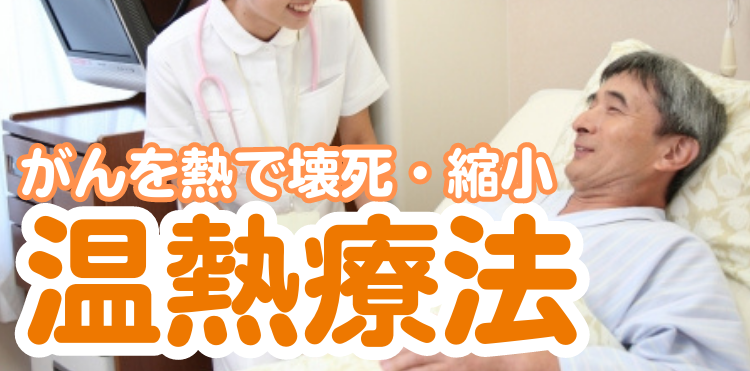







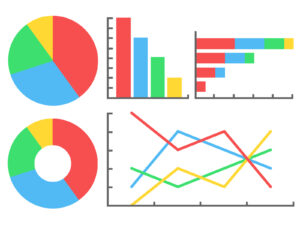

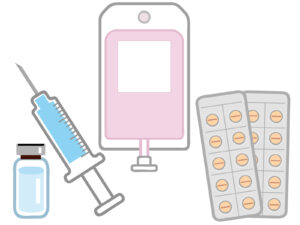

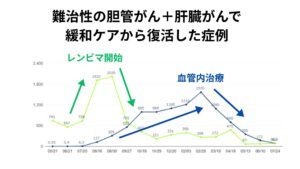

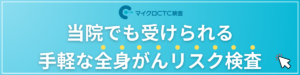
コメント